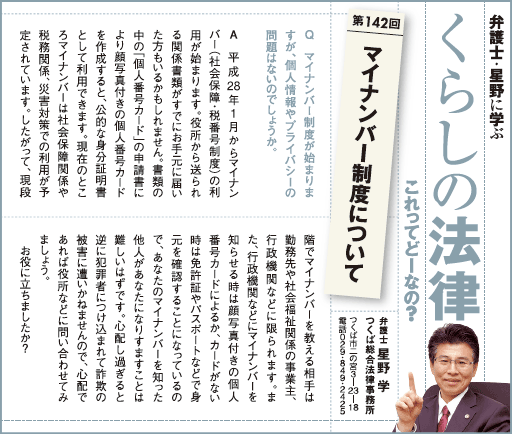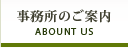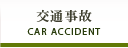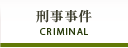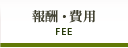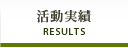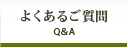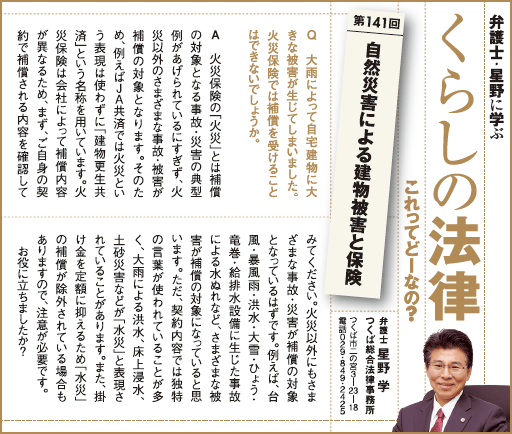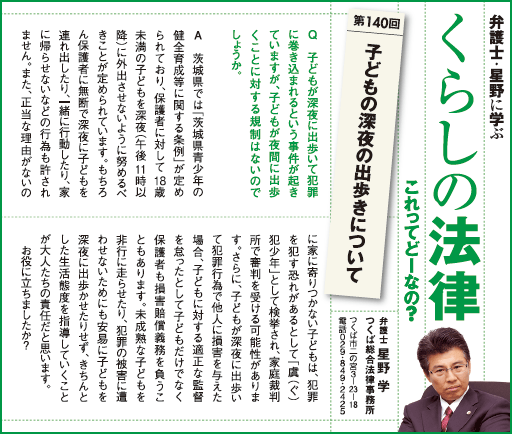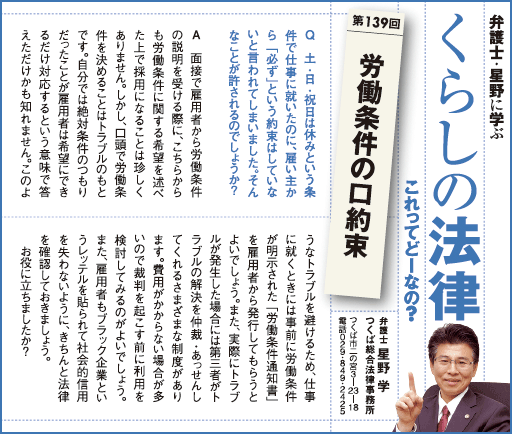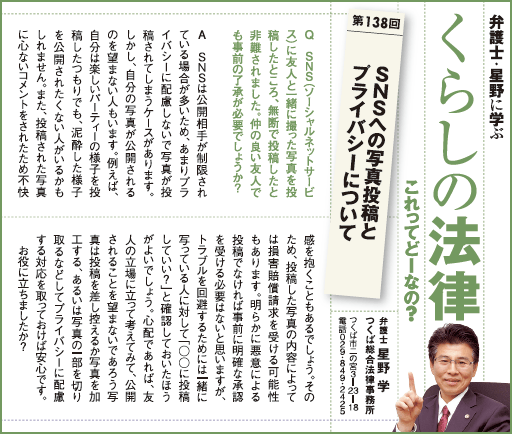Q
マイナンバー制度が始まりますが、個人情報やプライバシーの問題はないのでしょうか。
A
平成28年1月からマイナンバー(社会保障・税番号制度)の利用が始まります。役所から送られる関係書類がすでにお手元に届いた方もいるかもしれません。書類の中の「個人番号カード」の申請書により顔写真付きの個人番号カードを作成すると、公的な身分証明書として利用できます。
現在のところマイナンバーは社会保障関係や税務関係、災害対策での利用が予定されています。したがって、現段階でマイナンバーを教える相手は勤務先や社会福祉関係の事業主、行政機関などに限られます。
また、行政機関などにマイナンバーを知らせる時は顔写真付きの個人番号カードによるか、カードがない時は免許証やパスポートなどで身元を確認することになっているので、あなたのマイナンバーを知った他人があなたになりすますことは難しいはずです。
心配し過ぎると逆に犯罪者につけ込まれて詐欺の被害に遭いかねませんので、心配であれば役所などに問い合わせてみましょう。
お役に立ちましたか?